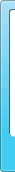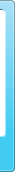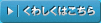http://www.hanbara.or.jp/
モバイルサイトにアクセス!
モバイルサイトにアクセス!
レインボ-プラザ
(愛川繊維会館)
開館時間/午前9時〜午後5時
体験・作品作り
/午前9時30分~〜午後3時30分
〒243-0307
神奈川県愛甲郡愛川町半原4410
TEL.046-281-0356
FAX.046-281-0866
神奈川県愛甲郡愛川町半原4410
TEL.046-281-0356
FAX.046-281-0866
114257
レインボープラザでは、手織り、藍染め、紙漉きなどの手作り体験ができます。はじめての方でも大丈夫!スタッフが丁寧にお手伝いします。わからないことは、お気軽にお問い合わせください。中津川の自然の中でスタッフ一同お待ちしています。
What's New
What's New
|
|
2024-07-22 | 夏の手作り体験フェア開催中、8月30日(金)まで。 |

|
2024-07-12 | 夏休み休館日のお知らせ:8月10日〜18日は休館させていただきます。 |

|
2024-06-27 | 相模蚕飼育の取り組みが神奈川新聞に掲載されました。 |

|
2024-07-01 | スタッフ募集のお知らせです。 |
いとの町半原の歴史
いとの町半原の歴史
|
|
ファイルダウンロード ( 2024-04-19 ・ 1203KB ) |
|---|---|
半原は江戸時代の文化4年(1807年)小島紋右衛門が桐生から八丁式撚糸機を導入したことが始まりと言われています。本格的な生産は水車を動力として利用されるようになった、嘉永年間(1848年)からであり、明治6年には洋式撚糸機(イタリ-式)の導入、大正の初めには愛川町を中心に愛甲、中、高座、津久井の4郡にまで撚糸業は発展し、半原、又は愛川の名で総称されました。
水車の動力が電機モ-ターに変わり、リング式撚糸機やボビン機などが半原撚糸の地位を不動のものとしました。これにともない各種の撚糸業が発展いたしました。 これらをさらに振興するため六つの団体を統合し愛川繊維団体連合会を創設、昭和42年法人化し、財団法人を設立、各種団体の指導育成・調査研究・福利厚生・教育及び情報の提供など地場産業として200年以上の伝統と歴史を守り、さらなる振興発展を図っています。 |
施設のご案内
施設のご案内
レインボープラザ/愛川繊維会館

■所在地
〒243-0307
神奈川県愛甲郡愛川町半原4410
TEL:046-281-0356
FAX:046-281-0866
運営管理:一般財団法人 繊維産業会
■各階の主な施設
1 F / 事務室、応接室、会議室、藍染め教室、紙漉き教室
2 F / 機械設備設置室(撚糸関係機械・組紐関係機械・織物関係機械)、手織り教室、組み紐、ホビ-室1・2
3 F /大会議室、多目的室1・2、手織り教室
2 F / 機械設備設置室(撚糸関係機械・組紐関係機械・織物関係機械)、手織り教室、組み紐、ホビ-室1・2
3 F /大会議室、多目的室1・2、手織り教室
バス
小田急「本厚木駅」から
神奈川中央交通バス①番のりば「半原行」にて終点「半原」下車すぐ裏 所要時間50分くらい
神奈川中央交通バス①番のりば「半原行」にて終点「半原」下車すぐ裏 所要時間50分くらい
JR横浜線「橋本駅」「相模原駅」「淵野辺駅」から
神奈川中央交通バス 「田名バスタ-ミナル」のりかえ「半原行」下車すぐ裏
「橋本駅」「相模原駅」「淵野辺駅」から「田名バスタ-ミナル」まで 所要時間 20分~30分くらい
「田名バスタ-ミナル」~「半原」 所要時間 30分くらい